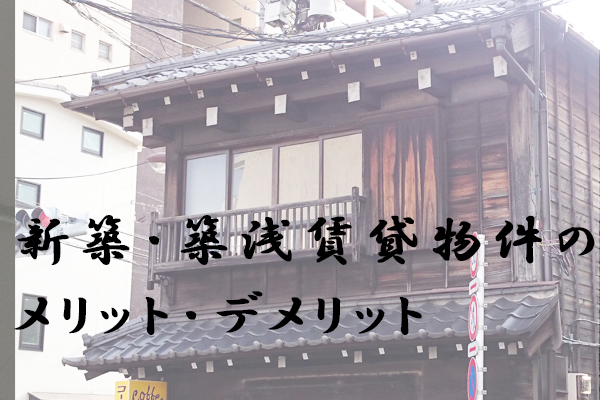新築・築浅の賃貸物件の定義とメリット・デメリットまとめ
意外と知られていない不動産用語
不動産広告を見るときに必ず見かけるのが「新築」という言葉です。
「新築」は文字通り新しく作られた物件のことですが、それではいつまでを「新しい」として認識するのでしょうか。
意外と正しい定義が知られていませんが、新築とは「竣工後1年未満で、未使用の物件」として定められているものです。
ですので仮に住宅メーカーなどが建売住宅を作ったとしても「新築物件」として売り出すことができる期限は1年までとなります。
その1年未満であっても、例えば入居した人がいて数ヶ月で出てしまったという場合は同じく「新築」ではなくなります。
ちなみに「竣工」というのはその建物の工事が完了をしたことを示す用語です。
新築の定義は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の第二条第2項に明確に記載されているので、不動産業界の慣例ではなくもっと強制力の強い縛りということになります。
もし定義に当てはまらない物件を「新築」として売り出した場合、広告表示の違反行為にあたりますので罰則の対象です。
「築浅」で示される年数は明確にされていない
一方で不動産業界内の慣例として使用されている言葉が「築浅」です。
「築浅」は「新築」と異なり法律で何らかの規定があるわけではありませんので、何年以内のことをそのように呼ぶかは広告を出す不動産業者の気持ちによります。
ですので「築浅」の築年数が3年なのか5年なのかは、実際に見てみないことには分からないというのが実情です。
しかしながら築年数が10年にもなるような物件を「築浅」と表現するのはあまりにも強弁が過ぎますので、一般的には5年までの物件に対して使用をされるのが通常となっています。
竣工後に入居者が見つからないまま1年が経過してしまったというような物件で、室内の魅力を表現するために用いるといったふうに考えるのがよいでしょう。
そもそも新築や築浅といった文言が広告に使用されるのは、新しい物件であるということから設備が充実していることを示したいという意向があるからです。
最近はオール電化住宅や自家発電装置がついている物件、災害に強い物件など特殊な設備を備えている住宅も多くありますが、そうしたことをアピールするためにも新築や築浅といった表現は便利です。
ただし借りる側や買う側にとって、新築や築浅物件は必ずしもメリットばかりというわけではありません。
確かにピカピカで最新設備のついている物件は魅力的なものですが、築年数が浅いことでその物件に隠された瑕疵が表面化していないこともあります。
一時期社会問題になったシックハウス症候群も新築物件で発覚をしていますので、新築や築浅に住むときにはそうしたことも可能性として頭に入れておいてください。